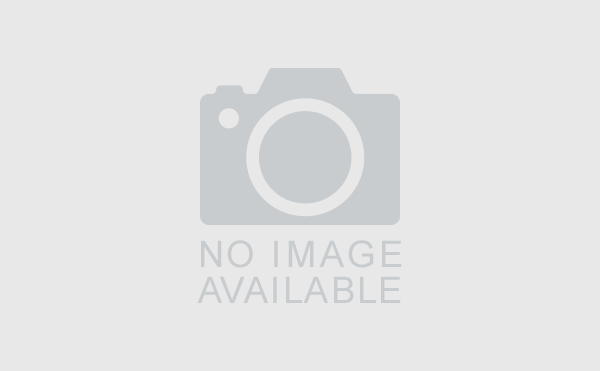認定審査会に伝わる特記を書くPart2|日常の意思決定

ポイント
実際の特記記載例を見てみると選択基準を理解していないと思われる特記と記載内容が多く見られます。
1.「2.特別な場合を除いてできる」を選択して、特記にはなにも記載がないケース。
この場合は、
①3群・4群・5群の特記を観れば選択理由が判るので特記記載は不要と考えている。
②日常的に行われる場面では決定できているので特記記載は不要と考えている。
いずれかの理由と思われます。
特記記載を省略できるのは「1.特別な場合でもできる」を選択した時であり、「2.特別な場合を除いてできる」を選択した場合は具体的な選択理由の記載が必要です。
2.「3.日常的に困難」を選択した場合の特記に「日常的に意思決定は行っていない」の記載がされているケース。
この場合は、意思決定は行っていないが「4.できない」には該当しないと考えているものと思われます。
日常の意思決定ができないと判断するのは、①意思疎通ができない②聞かれても答えられない(相手の話していることが理解できない)③意思決定できるかわからない場合であり、3-1意思の伝達が「ほとんど伝達できない」あるいは「できない」状態の方が該当すると解釈しているものと思われます。
そのため、ある程度意思疎通ができる方であれば、日頃意思決定を行っていない場合でも「4.できない」を選択せず、「3.日常的に困難」を選択しているものと思われます。
また、特記に「意思決定は行っていない」と記載した場合は選択肢は「できない」を選択するべきですが、自発的に意思決定していない場合でも、介護者に意向を聞かれそれに対して何らかの形で返答している場合があるものです。このような場合は「日常的に困難」に該当しますからその状況を記載するべきです。
記載例
| 記載例 | 選択された選択肢 | ポイント |
|---|---|---|
| 診療方針の合意には妻が支援している | 特別な場合以外可 | 「支援している」との援助の方法ではなく、対象者が合意や決定ができるか、合意には支援が必要かを記載するべきです |
| 治療方針の決定や合意は家族がしているが、自分で新聞をとり、TV番組も自分で選んでいている。また、必要な物は自分で娘に購入を頼んでいる | 特別な場合以外可 | 状況がわかる特記です |
| 自分では決定できない状態で、促しや指示を受けて行っている | 日常的に困難 | 決定が自発的に出来るかではなく、どの程度の決定を対象者ができるか、しているかを記載するべきです |
| 限られたことのみ、頷くなどして選択することができる | 日常的に困難 | 「限られた事のみ」の記載があるので日常的に困難であることが分かります |
| 認知症の進行で、自分で判断したり決定したりできない | 日常的に困難 | 日常的に困難ケースの特記にはこのような記載が多くみられます。特記にはどんなレベルのことを決定できるかの具体的に記載が求められます。飲食するかどうかやどこで過ごすなど限定したことを意向を聞いても決定できなければ「できない」を選択するべきでしょう |
| 日常の意思決定は行っていない。(3-1意思の伝達:ときどき伝達できるを選択) | 日常的に困難 | この項目は能力項目ですが特記は有無の記載になっています。「行っていない」ではなく「できない」とすべきです。日常的に困難な場合は何らかの決定はしているということなのでその状況を記載するべきです |
| 自分から希望したり判断することが出来ない | できない | 希望や判断が自発的かどうかは問いません。できないとするならその状況を具体的に記載するべきです |