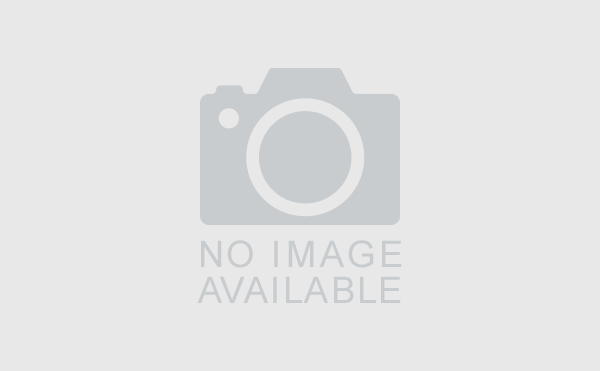話題|移乗と着座は違うことを理解すべき

移乗の選択基準
今回の話題は1次判定への影響が大きい「移乗」の選択基準についてです。
移乗の評価軸は介助の方法で、他の介助の方法項目と同様「日頃行われている、あるいは一定期間内に行われた移乗行為」に対する介助の方法で評価します。
移乗の定義は「でん部を移動させて椅子等に座る行為」であり、寝たきりの場合の体位交換も含まれます。そして、移乗行為が全くない場合は「行為が発生したことを想定して選択する」となっています。
軽度者の移乗行為
認定調査員研修などでは、定義に含まれない軽度者の移乗、具体的には「歩いて移動して座る行為」いわゆる着座行為をどう評価するかが話題になり、その中では間違った解釈をしている調査員が多いと指摘されることもあります。
この「歩いて移動して座る行為、いわゆる着座行為をどう評価するか」についての厚労省の見解は
①軽度者の「ベッド→歩行→便座(着座)」は移乗行為ではない
②移乗については類似行為という考え方は存在しない
つまり、歩行して移動して着座する行為は、調査項目としての移乗行為にはあたらず、また、行為が発生しない場合の選択根拠とする類似行為でもないとしています。
認定調査員から見た「移乗」の解釈と評価
調査員は、介助の方法の項目の場合「日頃行われている生活上の状況」で判断・選択するものと承知しています。
移乗の場合、日頃寝たきりや車椅子を使用している場合は項目の定義に該当するので迷うことはありませんが、車椅子を使用していない場合などは定義に該当しないので、日常的に行われている類似的行為「歩いて移動して座る行為(着座)」で判断する調査員がほとんどだと思います(私もその中の一人です)。
調査員は「日常的に行われている行為に対する評価」という意識があり、どうしても頻度の多い「着座」を移乗として評価してしまいがちなのです。
実際に周りの移乗の特記を見ても、着座を移乗と判断し、その介助の方法で評価している場合がほとんどです。そして、その選択や特記に対して保険者側から「定義に該当しない」などの照会が来ることはほとんどないようです。
これは、保険者の認識は厚労省の見解と同じではあるが「軽度者の『ベッド→歩行→便座(着座)』をどう扱うか」については、下記のように必ずしも考えが統一されていないためと思われます。
定義に規定する移乗行為がない場合
<定義に規定する移乗行為がない場合の着座に対する保険者の考え>
①移乗には該当しないので「介助されていない」を選択し、一次判定に反映させるかは特記内容で審査会が判断する
②移乗には該当せず、移乗の機会がない状態と判断し、調査上の留意点にある「規定する移乗行為がない場合は、移乗行為が生じた場合を想定し適切な介助を選択」とする
この2通りの考えがあり、調査員が着座を移乗と解釈していても個別の照会は出さないのだと思われます。そして、現在の厚労省の要介護認定適正化事業や認定調査員能力向上研修会では②の考えかたを指導しています。
調査員の解釈は厚労省の指導内容とは必ずしも一致していませんが、移乗行為が生じた場合を想定して適切な介助を選択しても、結果的に調査員が選択した、着座の際に実際に行われている介助の方法と同じになる場合がほとんどです。それゆえ保険者も調査員の解釈の誤りをその都度指摘することはせずに調査員の評価・選択を受け入れているものと思われます。
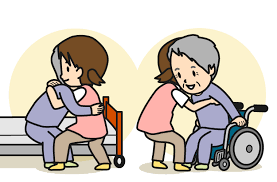
特記にはどう書くべきか?
認定調査員研修などで示されているのは、軽度者の移乗(着座)の場合、「日常生活において移乗行為は発生しない」と記載した上で、移乗行為が生じた場合を想定して適切な介助を選択し、そのように判断した具体的な状況を特記記載するように指導しています。
<例>
・日常生活において移乗行為は発生しない。移乗行為があると想定すると、1群の立位や立ち上がり、歩行などの状況から介助は必要ないと判断した。
・日常生活において移乗行為は発生しない。移乗行為があると想定すると、便座などから自力での立ち上がりが困難で引き上げ介助が必要なことから一部介助を選択
補足について
なお、当サイトでは、調査員テキストに規定された移乗を「直接移乗」、軽度者の“歩いて移動して椅子等に座る”場合を「間接移乗」と表現し、間接移乗の場合も直接移乗と同様に調査員テキストに規定された介助の方法で選択するとしてきました。
この間接移乗の選択肢は、先に述べた通り、椅子や便器の着座の際などに実際に行われている介助の方法で選択するもので、結果的に移乗行為が発生したことを想定して選択する場合とほぼ同じになります。そのため、この解釈に変更はありませんが次のような補足を追加しました。
-補足-
この記事を投稿している時点では、保険者の考え方は“対象者が歩ける場合は移乗行為は発生していない”としたうえで、選択肢は「移乗行為が発生していないので『介助されていない』を選択するとの判断と『選択肢は移乗行為が発生したことを想定して適切な介助の方法を選択する』との判断が混在していました。
その後も「対象者が歩いて移動する場合は移乗行為は発生していない」とする考えかたは変わっていませんが、近年は「介助されていない」の選択ではなく、「移乗行為が発生した場合を想定して、適切な介助の方法を選択する」ことが基本的な考え方になっています。