話題|認知症分野の第一人者が自身の認知症を公表
長谷川和夫医師が自身の認知症を公表
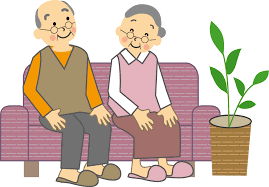
認知症の判定などに広く使われている「長谷川式認知症スケール(HDS-R)」を開発した医師の長谷川和夫さんが、自身が認知症であることを公表し,新聞のインタビューに答えていますので紹介したいと思います。
長谷川和夫医師は精神科医で89歳。現在は認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長、聖マリアンナ医科大学名誉教授の役職についています。
1974年に簡易認知症スクリーニング検査のための長谷川式認知症スケールを発表、現在もこのスケールが主治医意見書での認知症の判断ツールとして多く使われています。
その後医療ディケアを開設したり、「痴呆」から「認知症」への名称変更にも関わって来た、認知症専門医です。
昨年、記憶力低下を自覚して専門病院に奥様同伴で受診し「嗜銀顆粒性認知症」の診断を受けたとの事。また、認知症の診断を受けたことに対しては「物忘れ以上のものを自覚していたから、あー、やっぱりと思い、戸惑いはなかった」と話しています。
また、自身が認知症を公表することについては「認知症の専門家として世間に知られている自分が告白することで、普通に生活していることが分かってもらえ、認知症の人の環境にもプラスになると思った」と答えています。
「今、1日をどう過ごしているか?」との質問には、「朝6時半ごろ起きて、朝昼晩の食事。その間に散歩したり図書館や近所のコーヒー店に行ったりしている。今日が何月何日なのか、時間がどのくらい経過したかはっきりしないが不便を感じることはない。夫婦2人の生活でやることは毎日ほぼ同じだから」と答えています。
「認知症本人に質問はするが、本人の話を聞く人は少ない…」

インタビューの中で、「周囲は(認知症の)本人に尋ねることはしても、本当にその人の話を聞いていることは少ないように思う。確かに、出来ないことは増えていくけれども」と語っており,インタビュー記事の中に、スーツ姿で椅子に座り杖を前に立てそれに両手を置いて少し寂しげな表情で写っている氏の写真があり、この写真とこの言葉が印象的です。
介護認定調査の現場でも認知症状やBPSDについて介護者や家族の話を聞くことはあっても、本人に対しては質問をするだけで、対象者本人の気持ちや話を聞くことはほとんどしません。
むしろ本人の話を聞くことでBPSDに至った理由が見えて来て、果たして家族がBPSDと感じている行為は場面や目的から見て不適切だろうか、本当にBPSDと言えるのだろうか、と自分が混乱し判断に迷うことを嫌い、あえて聞かないという選択をしている場合もあります。
また、場所を変えて本人がいない所で家族などに聴き取りをするのも、"本人の前では言い難いことがあるから"という理由だけではなく、"本人に反論されて収拾がつかなくなることが心配"という側面もあります。
前回の「今月の話題~4月~」で紹介したように、対象者本人から保険者側へ届いた認定調査員への苦情の中に「話を聞いてくれない」「自分に認知症があるかのような扱いを受けた」というのがありました。
要介護認定調査を効率的にできるだけ短時間で実施するためには、各基本調査項目についてある程度事務的に聞き取りせざるをえません。
その中で「対象者は認知症がある」との先入観があると、対象者の少しだけ変わった行動すべてをBPSDと捉えてしまいがちです。
しかし対象者本人に話を聞くと、なぜそのような行動をとったのかが納得できる場合が少なくありません。
認定調査時間は短いに越したことはありませんが、時間の許す範囲で対象者自身の話を聞くことが必要なのだと、このインタビュー記事を読んで改めて感じた次第です。
皆さんはどう思いますか?
