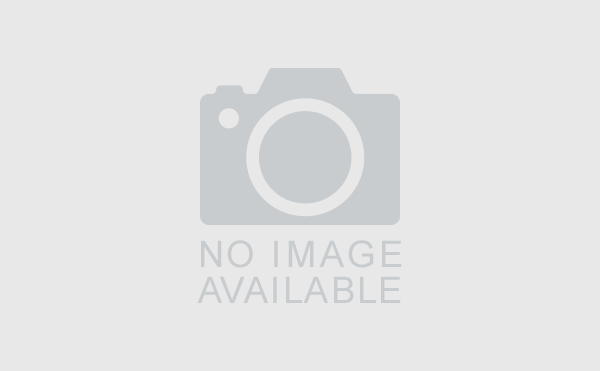話題|厚労省の能力向上研修会に見る「座位保持‐できない」の解釈の変化

座位保持は判断に悩む項目
今回は座位保持の解釈に変化が出て来ていることを報告したいと思います。
2年ほど前の認定調査員現任研修で次のような出題がありました。
Q:「座位保持」について、寝たきり状態で、経管栄養時に30°に背を起こしている場合の選択肢は?
A:できない
これについて「今までは、テキストにある『できない』とする3つのケースが『できない』に該当すると指導を受けてきたが、この選択肢で良いのか?」と質問したところ、「30°程度の背上げは、座位保持ができないと判断します」との説明でした。
その後の調査で、「支えてもらえばできる」を選択して、特記に「ベッド上生活で、経管栄養時には毎回45°のギャッチアップをしている」と記載して提出したところ、審査会事務局から「45°のギャッチアップは座位保持とはいえない」との照会があり、結果的に「できない」に変更になったことがありました。
上記の2つの解釈はいずれも「背上げ角度」がポイントとの保険者側の返答であったため、「『支えてもらえばできる』と判断する具体的な背上げ角度を教えて欲しい」と連絡しましたが、その後この質問に対する返答はありませんでした。
座位保持については、当サイトでも「判断に迷う項目」として話題に取り上げ、SNSで全国の調査員さんに背上げ角度のアンケートに答えていただくなどしてきました。その結果アンケートの答えてくれた調査員の約70%が調査員テキストにある3つの状態の場合に「できない」を選択するという結果でした。同時に「支えてもらえばできる」と「できない」の選択に迷う、という声が多く聞かれています。
Webサイトから見る保険者の見解
認定調査項目に関連するWebサイトの記事は各保険者から数多く発信されていますが、座位保持について具体的な例や角度などをあげている保険者は少なく、ほとんどの場合「能力で判断するもので、日頃の様子で判断するものではない」「座位を保つための角度に制限はない」の2点をあげているのみです。
ちなみに調査員テキストでは「できない」に該当するのは以下の3つの状態であると明示しています。
①長期間(おおむね1ヶ月)にわたり水平な体位しかとったことがない場合。
②医学的理由で座位保持が認められていない場合。
③背骨・股関節の状態により体幹の屈曲ができない場合
各保険者の判断・考え方も当然ながらこれに準じており、保険者のホームページなどで紹介されている例には次のようなものがあります。
例1 名古屋市のQ&A
Q:ベッド上の生活のみで、経鼻経管栄養時ベッドの背もたれを支えとし45度(場合によっては両脇をクッションで支えて固定)の状態を10分以上保つことのできる場合、またはリクライニング車椅子で背もたれを支えとし45度の状態を保つことができる場合は、座位保持「3.支えてもらえばできる」と判断してよろしいか。
↓
A:ギャッジベッドや車いすの背もたれが支えとして機能し、座位保持ができる場合は、「3.支えてもらえばできる」と判断します。また、どのような状況が座位を保持した状況かは、調査対象者の日頃の状況に基づいて判断します。
例2 大和郡山市
数分であれば座れるが、10 分は背もたれがあっても保持できなので『できない』を選択。
→ 誤り
<誤りとする理由>
座位保持の選択基準「4.できない」は、テキストにあるように
・長期間にわたり水平な体位しかとったことがない場合
・医学的理由により座位保持が認められていない場合背骨や股関節の状態により体幹の屈曲ができない場合
のみ「できない」となります。
「10 分間」の目安は、「1.できる」「2.支えればできる」「3.支えてもらえればできる」のいずれに該当するかを判断する基準となります
例3 茨木市
伸展拘縮で、電動ベッドのギャッチアップをしても45℃位(目安)しか上げられない。(常に仰臥位)→できない ※ギャッチアップの具体的な角度の定義はない。 ↓
例4 福島県
経管栄養時はベッドを 30 度程度まで起こし、入浴時はリクライニング式車椅子を使用し、30~40 度程度で座位を保つ。あまり起こすと首が前に倒れるなどの危険があると職員が話す。座位保持とはいえない状態のため「4.できない」を選択。
例1と例2の選択理由は「できないとする3つのケースに該当しない」が判断理由で、特に例1は普段座位になっていない例としてよくあるケースで、私もこの場合は「支えてもらえばできる」を選択していました。例3はできないとするケースの③に該当し、例4は同じく②に該当するとの解釈です。すなわち全例ともにテキストに明示されている「できないとする3つのケース」に該当することが「できない」の選択根拠となっています。
要介護認定適正化事業 業務分析データにおける「座位保持」の選択肢の割合
ちなみに、厚労省の要介護認定適正化事業、業務分析データ「座位保持」では
1‐5 座位保持 全国平均(中央値)の推移(%)
(R1~R4年度は10/1~3/31、R5年度は4/1~9/30)
| 選択肢 | R1年度 | R2年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|---|
| できる | 34.5 | 36.0 | 31.2 | 30.3 |
| 自分で支えればできる | 34.2 | 33.4 | 33.0 | 34.8 |
| 支えが必要 | 29.4 | 28.8 | 32.5 | 31.8 |
| できない | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
各年度による各選択肢の分布割合に大きな変化は見られず、全体で「できない」に該当するのは調査対象者のわずか1.8~1.9%という結果になっています。これは「できない」の選択基準が限定されていることが影響していると考えられます。
最近の研修会での「座位保持‐できない」に対する解釈の変化
しかし、最近「できない」に該当する選択基準の中の“長期間にわたり水平な体位しかとったことがない場合”の解釈が変わってきているようです。
最新の能力向上研修会では、「判断のポイントは、背上げ角度ではなく、“日頃座位になっているか”どうかにある」と指導しています。
具体的には、日頃寝たきりで、常時水平位もしくは水平位に近い状態で過ごしている方が、食事または経管栄養の際にのみ誤えん防止目的にベッドの背上げなどをしている、また、入浴の際だけリクライニング車椅子を使用して移動している場合などは「日頃座位になっているとは言えない」として、その背上げ角度に拘わらず「長期間(おおむね1か月)にわたり水平位しかとったことがない場合」に該当すると説明しています。
2年前の現任研修でのQ&Aやその後の審査会事務局からの照会も「できる出来ないは、背上げ角度ではなく日頃の座位の機会で判断する」ということであれば納得がいきます。しかし、照会の内容などを見ると審査会事務局内がこの解釈で意見統一がされているとは必ずしも言えないようです。
特記の記載はどうするか
一番の大もとで指導している訳ですから各都道府県を通して各保険者も承知していると思いますが、各保険者の審査会事務局内で解釈が統一されているとは限りませんので、特記には次の2点を記載することをお勧めします。
1.日頃寝たきり状態であり、上体を起こしている時間はほとんどないこと
2.座位になる目的は誤えん防止や移動のためであり、且つ一時的であること
まとめ
座位保持について、普段寝たきりであっても誤えん防止目的にギャッチアップなどの背上げをしている場合、また、入浴の際などに一時的にリクライニング車椅子を利用している場合、「何度までの背上げ角度が座位に該当するのか」の疑問が多く聞かれる。
しかし、問題は背上げ角度ではなく、「例え背上げ角度が低い場合であっても日頃から座位になる機会があれば『できない』には該当せず、逆に背上げをしていても誤えん防止目的であったり、一時的な場合にのみ座位になっている場合は”長期間にわたり水平な体位しかとったことがない”と判断して『できない』を選択する」との解説が、「令和2年度 厚労省 要介護認定適正化事業 認定調査員能力向上研修会 認定調査の基本的な考え方」で行われている。