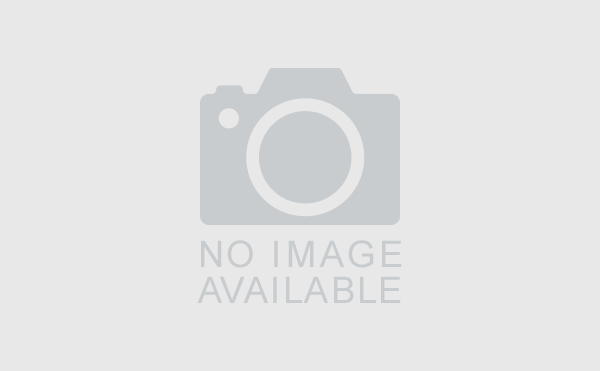話題|一般病院に入院している認知症対象者の認知症状の聞き取りポイント
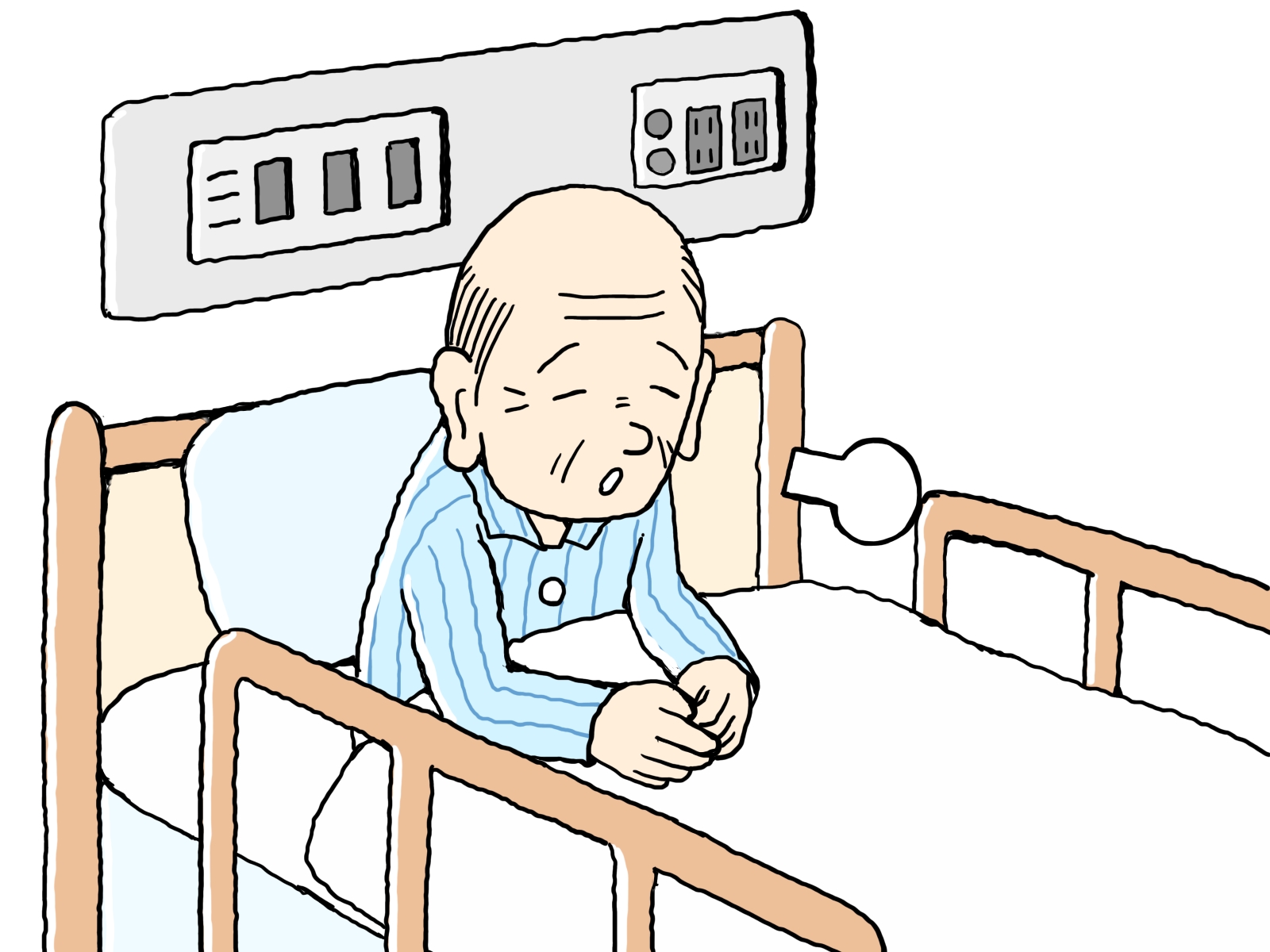
一般病院に入院している認知症対象者の認知症状の聞き取りのポイント
1.一般病院における認知症状の聞き取りの難しさ
一般病院に入院している方の認定調査の場合、能力や介護の手間などは看護師さんから聞き出しやすいですが、認知症にかかわる質問には「特に問題になるようなことはない」とされる場合が多くあります。
入院という環境変化で以前みられていた認知症状が実際に出なくなったことも考えられますが、実際はそうではなく情報が少ないという一般病院ならではの理由があります。
2.一般病院に入院している場合の認知症状の情報が少ない理由
①入院中はベッド中心の生活のため他人との関わりが少なく、会話も少ないので認知症状が表面に出ない
②一般病院は入院疾患の治療が目的なので、治療に支障のない、周りの患者の迷惑にならない程度の認知症状は“その人の性格”とみなされ問題視されない
③患者の言動は身体状況から来る場合が多いので、違和感のある行動でもそれが認知症の症状かどうか看護師には判断がつかない
④在宅や施設の場合は、以前こんなことができていたが最近はしなくなった、出来なくなったなどの情報があるが、入院時の情報には含まれない
3.認定調査の実際
①本人からの聞き取りと病院側からの聞き取り、どちらを先にするべきか?
対象者への聞き取りが前・後どちらでも可能であれば、本人からの聞き取りを済ませてから看護師からの聞き取りをするべきです。これは本人からの聞き取りで感じた不整合や疑問を確認できるからです。
②対象者への聞き取りのポイント
対象者へ聞き取りする場合、直接調査項目に関係のない話題でも対象者と出来るだけ多く話をすることが大切です。そのやりとりの中で記憶や判断力などの大まかな状態像が分かってきます。
そんな中でも是非確認したいのは、入院までの経過、いつから入院しているか、何の病気で入院したか、どんな治療をしているかなどを聞くことです。多少間違いがあっても構わず、認知機能低下のない方は答えられますが、記憶や理解力が低下している方は答えられない場合が多く、看護師への聞き取りで「目立った物忘れはない」と言われた方の中には、なんで自分が入院しているかや手術したことなどを全く覚えていない方がいます。
そしてこの質問の後に3群の項目の質問をすると「日課の理解」などの評価がしやすくなります。また、「短期記憶」については看護師側では判断できない時も多いため、可能であれば3品テストを実施することを勧めます。
③看護師への聞き取りのポイント
入院日、主病名、治療方法などを聞き取り、対象者の話と合致しているかを確認します。その後に3・4群の項目を具体的な例を出して確認をします。
-3群-
・毎日の日課を理解:大まかな時間の感覚はあるか、定期的にリハビリをしていることを理解しているか
・短期記憶:話したことをすぐに忘れる、当日にリハビリしたことや家族の面会があった事を覚えているか
-4群-
4群の質問をする際に「認知症状があるか」「何か問題行動はあるか」など全体をひとくくりにして質問すると、「年齢相応」あるいは「ない」と返答される場合があるため当然ながら各項目ごとに質問します。
また、項目ごとに質問した場合でも「被害的になることはあるか」「作話はあるか」などテキストに載っている項目タイトルのままで質問すると看護師側では該当するか判断できない場合があるため、「このようなことはありませんか?」と項目ごとに具体的な例を出して質問することが大切です。
・被害的になる:無理やり入院させられた、周りの人が自分に意地悪している、などの話はないか
・作話:現在の状況に合致した話をするか、あり得ないと思うような非現実的な話はないか
・ひどい物忘れ:看護師が話したことを覚えているか、何度も同じ説明をする必要はないか、やり方を教えても忘れてしまいリハビリが進まないなどの話はないか
・自分勝手に行動する:オムツ外し、常時使用の指示がある装具やチューブなどを勝手に外してしまう、必要な医療行為に抵抗するためやむを得ず拘束をする必要がある、危険防止のために各種センサーを使用している、などはないか
・話がまとまらない:入院の必要性を理解できず話が噛み合わない、聞いたことを理解できず話が進まない、また、会話にならないので周りが対象者に話を合わせている状態ではないのか
-5群-
・日常の意思決定:病状説明、治療方針の説明、看護計画などは誰に話をして、誰に了解を得ているのか、また、ナースコールを押して自分の要求や訴えはできるか、下着を交換したい・○○が欲しいので家族に連絡して欲しいなどと言うことはあるか
4.まとめ
認知症の既往がある方が認知症以外の病気で一般病院に入院した場合、特に長期入院ではない場合はそれまでの認知症症状が表に出ない場合があります。
それは、環境が変わって認知症状が出なくなったのではなく、ベッド中心の生活になって他人との関わりが減り、自分の考えを表出する機会が減ったためと思われます。実際に第3群の認知機能の質問に答えられないにも拘らず、第4群の精神・行動障害の項目に何も該当がないようなケースも見られます。
第2群の生活機能や第5群の社会生活への適応の項目は実際の介護の手間を評価するものなので調査員の質問の仕方で選択肢が大きく変わることはありませんが、第4群の精神・行動障害の有無は調査員の具体的な質問によって対象者の日頃の状況を引き出すことに繋がり選択肢にも影響してきます。そのため、病院での看護師などへの聞き取りには、できるだけ具体的な例を出してそのような言動がないかを確認することが必要です。